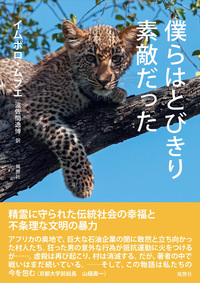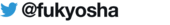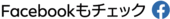目次
(原著:How Beautiful We Were、Imbolo Mbue著、2021年3月、Random House社)
目次
スーラ
⼦供たち
ボンゴ
⼦供たち
サヘル
⼦供たち
ヤヤ
⼦供たち
ジュバ
⼦供たち
訳者解説:粘り強い文学
《登場人物》
スーラ:コサワ村の少女
マラボ:スーラの父
サヘル:スーラの母
ボンゴ:マラボの弟
ヤヤ:マラボの母
ジュバ:スーラの弟
ルサカ:スーラの同級生の父親
ウォジャ・ベキ:コサワ村の村長
コンガ:コサワの狂人
ジャカニ:双子の霊媒師
サカニ:双子の治療師
〈リーダー〉:ペクストンの社員
〈病気の人〉: ペクストンの社員
〈丸い人〉: ペクストンの社員
フィッシュ:ペクストンの上級監督
オースティン:新聞記者。〈病気の人〉の甥
〈いけてる人〉:コサワ回復運動のスタッフ
〈かわいい人〉:コサワ回復運動のスタッフ
内容説明
精霊に守られた伝統社会の幸福と不条理な文明の暴力
アフリカの奥地で、巨大な石油企業の闇に敢然と立ち向かった村人たち。狂った男の意外な行為が抵抗運動に火をつけるが……。虐殺は再び起こり、村は消滅する。だが、著者の中で戦いはまだ続いている。──そして、この物語は私たちの今を包む(京都大学前総長 山極壽一氏推薦文)
ニューヨーク・タイムズで2021年の「ベスト10冊」
PEN/フォークナー最終候補作
*********************************************
本文冒頭より
僕たちは、もうこれでおしまいだってことに気づいていなかったんだ。気づかないなんてありえなかったのに。空が酸を降らせ、川が緑に変色し始めたとき、僕たちの土地がまさにいま息絶えようとしていることを、見過ごしてはならなかったのに。でもよくよく考えてみると、あの連中が僕たちに気づかせまいとしていたあの状況では、どうやっても気づけなかったんじゃないだろうか。僕たちがふらつき、よろめき、倒れ、かぼそい小枝みたいにぽきんと折れ始めたとき、あいつらは僕たちに「こんなことはすぐに終わりますから」「すぐにみなさんの体調はよくなりますからね」と言った。連中は村の集会にやって来て、状況を説明してくださいますかと僕たちに求めた。彼らを信じなければならない、あいつらは僕たちにそう言った。
彼らの顔に唾を吐き、最もふさわしい名前をつけてやるべきだったんだ。偽善者、野蛮人、恥知らず、悪魔というふうに。彼らの母親や祖母を呪い、父親に罵詈雑言を投げつけ、口にするのもおぞましい災いがあいつらの子供たちに降りかかるよう祈るべきだったのだ。僕たちは彼らを憎み、彼らとの集会を憎んだが、集会には欠かさず参加した。八週間ごとに村の広場に出かけていっては彼らの話を聞いたんだ。僕たちは死にかけていて、なすすべがなかったから。僕たちは怯え、集会にしがみつくしかなかった。
彼らが指定した集会の日、僕たちは議論をひと言も聞き逃すまいと、学校から走って帰ってきて、いそいそと家の雑用をこなした。井戸から水を汲み、家の敷地をうろついている山羊や鶏を竹で拵えた囲いに追い立て、前庭に落ちている葉や小枝を掃き集めた。夕食後には山のように積み重なったお皿と鉄鍋を洗った。集会が始まるまでけっこう時間はあったけど、僕らは小屋を出た─立派なスーツを着て、ぴかぴかに磨きあげた革靴を履いたあの連中が広場に足を踏み入れる前に、そこに到着しておきたかったからだ。母さんたちも早々と駆けつけた。父さんたちも。ビッグリバーの向こうの森でやってた仕事を途中で切り上げて。手のひらと裸足の足は、汚染された大地の土にまみれていた。明日になればまた仕事が待っているよ、だけど、ペクストン社の男たちの話を聞く機会はそうそうないからね、と父さんたちは言った。慈悲深くも残酷な太陽の下で何時間も働いてへとへとになり、もう体に力が入らなくなっているというのに、集会にやって来たんだ。話し合いには全員が参加しなければならない、父さんたちはそう考えていた。
来てないのは、村に住んでいる狂人のコンガ一人だけ。コンガには僕たちの苦しみなんか、どこ吹く風だった。いま世間で何が起きているのか、これから先何が起きるのか、そんなことにはお構いなく日々を送っていた。彼は、僕たちが何かに追い立てられるように早足で歩を進めるのをよそに、学校の敷地でいびきをかき、よだれを垂らして寝ていた。そうでなければ目を閉じて、寝返りをうちながら体を掻き、何やらぶつぶつ独り言を言っていた。精霊が支配し、人間は無力であるような世界に彼は一人で閉じ込められていたんだ。ペクストンのことなんて知る由もなかった。……
訳者解説
粘り強い文学
波佐間逸博
この『僕らはとびきり素敵だった』(How Beautiful We Were)という美しくも、もの悲しく不吉なタイトルを冠せられた長編小説は、二〇二一年の三月にランダムハウス社から単行本として出版された。
当初、二〇二〇年六月に出版されることになっていたが、新型コロナウイルス感染拡大の影響で出版は延期された。パンデミックの最初期、マンハッタンでは救急車や警察車両のサイレンが絶え間なく響き渡り、出版延期の決定は作者イムボロ・ムブエを途方に暮れさせた。
いたたまれなくなった彼女は夫と子供たちとともにハドソンバレーに避難した。気の遠くなるような(と本人が語っている)月日の流れのあとでようやく『僕らはとびきり素敵だった』が出版されると、思慮深い、共感のメッセージがニューヨーク州北部の静かな町に届きはじめる。
「この小説が扱うテーマの重さや物語の広がりを考えると、目指すものが大きすぎて執筆が暗礁にのりあげてしまう危険はかなり高かったんじゃないかな。でも、ムブエは月に向かって腕を伸ばし、最後にはそれをしっかりと手につかんだんだ」と小説家のトチ・オニェブチはアメリカ公共ラジオ放送で語った。
「ムブエの描くこの壮大な物語の魅力は、権力と腐敗をめぐる単純な勧善懲悪の物語という枠を越え、もっと複雑で奥行きのあるテーマを巧みに描き切っている点にある。ダビデとゴリアテのような対立として始まる小説世界は、資本主義と植民地主義という悪意ある欲望機械の緻密な探求に昇華している」と、小説家でジャーナリストでもあるオマー・エル・アッカドは『ニューヨーク・タイムズ』に詳細な書評を寄稿した。
『ワシントン・ポスト』も紙面を大きく使って、小説の美質を分析した。「『僕らはとびきり素敵だった』は、自然の中で営まれている共同体的な生活にむけられた、はっとするくらいあたたかなラブレターである。しかし、それは手放しのアフリカ賛美などではない。人々の抱えている矛盾や限界を直視し、人間的な良識と利己主義の両面をあますところなく丹念に描写している」
そして『カーカス・レビュー』は「この小説の数ある美点の中でも特筆すべきは、環境破壊という悪夢を背景に、世の無関心にふきさられてもなお自らの価値を世界に訴えつづける人間の姿を、鮮烈かつ感動的に描き出していることだ。悲しみで胸がしめつけられるほどのやりきれなさと、立ち向かう意志を呼び起こすほどの怒りを抱かせる、現代的で力強い小説だ」と、簡潔だが要を得た賛辞をおくっている。
称賛の声はやまず、ほどなくして本書はPEN/フォークナー最終候補作となり、『ピープル』『エスクァイア』『マリ・クレール』をふくむ数多くの主要メディアで「今年の最良の一冊」に選ばれた。
『僕らはとびきり素敵だった』は、ムブエにとって生まれて初めて手がけた物語なのだが、出版された順番からいくと二作目の小説ということになる(詳しくはまたあとで)。デビュー作は、リーマン・ブラザーズ経営破綻後のアメリカを生きるカメルーン系移民を描いた『Behold the Dreamers(夢見る人びと)』で、二〇一六年にランダムハウス社から出版された。この作品もまた、批評的にも商業的にも大成功をおさめていた。ドル建てで七桁のアドバンス(前払い印税)を獲得し、複数のレビューで「二十一世紀アメリカ文学の傑作」と絶賛され、オプラズ・ブック・クラブに選出され、『ニューヨーク・タイムズ』をはじめ各種ベストセラー・ランキングに名を連ね、二〇一七年のPEN/フォークナー賞を受賞し、映画化の権利をソニーが買い取った(監督はジョージ・クルーニーに決定)。
当然、読者たちは大きな期待を持って、ムブエの次作を待ち望むことになった。
二作目はころぶ、というジンクスがアメリカにはある。日本のプロ野球でも似たような傾向が指摘されることがあるけれど、アメリカではこの不幸な雲はジャンルを選ばないらしい。たとえば「シンディ・ローパーは『ガールズ・ジャスト・ワナ・ハヴ・ファン』の成功を繰り返すことができるか、それともワンヒットワンダーで終わるのか」とか「ケヴィン・コスナーは『ダンス・ウィズ・ウルブズ』のような傑作をふたたび世に送り出すことができるか」とか「ラフ・シモンズのプラダ・コレクション第二弾は前回と同じくらい魅力的だろうか」というように。人は期待を裏切るまいと考えた時、肩に余計な力が入り、体が硬くなり、フットワークが重くなり、頭がぐつぐつ煮詰まってしまうものなのかもしれない。
だが、この非凡な作家は書き始めてからじつに十七年もの長く曲がりくねった道を歩きつくし、二作目『僕らはとびきり素敵だった』を、その執筆にかけられた年月に見合うだけの、深く掘り下げられた、切実で濃密な物語にしあげることができた。
(後略)
*********************************************
《著者について》
Imbolo Mbue(イムボロ・ムブエ)
デビュー小説『BEHOLD THE DREAMERS』によりPEN/フォークナー賞フィクション部門、ブルー・メトロポリス「変革への言葉」賞を受賞。オプラズ・ブッククラブにも選ばれた。二作目の本書『僕らはとびきり素敵だった』は、ニューヨーク・タイムズで2021年の「ベスト10冊」に選ばれた。彼女の作品は20カ国語以上に翻訳されている。カメルーンのリンベ出身で、ラトガース大学とコロンビア大学を卒業後、現在ニューヨークに在住。
(詳細は本書の訳者解説348頁以降を参照)
《訳者について》
波佐間 逸博(はざま いつひろ)
1971年東京生まれ。東洋大学社会学部教員。
早稲田大学を卒業後、京都大学大学院に進学し、1998年よりウガンダとケニアの国境地域でナイル系の遊牧民家族と暮らし、生態人類学的なフィールドワークを行なっている。
著書に『牧畜世界の共生論理──カリモジョンとドドスの民族誌』、『レジリエンスは動詞である──アフリカ遊牧社会からの関係/脈絡論アプローチ』(共著)、『Citizenship in Motion』(共編著)、訳書としてキリン・ナラヤン著『文章に生きる──チェーホフとともに、エスノグラフィーを描く』など。