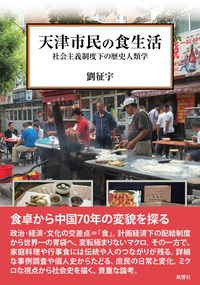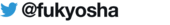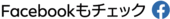目次
序章
第一節 研究の背景と目的
第二節 研究の方法
第三節 本書の構成
第一章 天津都市部の食文化の概観
第一節 天津の地理的環境と物産の種類
第二節 近代の都市発展と料理の特徴
第三節 近代天津住民の食生活
第二章 現在の天津都市住民の食生活
:六二世帯の事例調査からみる日常食と行事食の実態
第一節 都市家庭の食生活の実態
第二節 ある中流層家庭の食生活―老婦人Z及び息子L夫婦を事例として
第三節 まとめ
第三章 個人の嗜好と家族関係からみる家庭食事の持続と変化
:三人のライフヒストリーからみる都市家庭の食生活史
第一節 老婦人Zの食生活史
第二節 息子Lの食生活史
第三節 息子の妻Sの食生活史
第四節 まとめ
第四章 食物の販売ルートの変化に応じる都市住民の食の実践
:親族・親友関係や食の経験の活用からみる食材入手の対処
第一節 食物の自由売買期(一九五三年まで)
:富の格差による食材入手の差異
第二節 配給制の実施期(一九五三〜一九九三年)
:食をめぐる国家の規制に対する人間関係や経験の活用
第三節 自由売買の復帰期(一九九三年〜現在)
:情報化社会への転換による食消費の多様性
第四節 まとめ
終章 結論と展望
あとがき
付録
付表
年表
参考文献
索引
内容説明
食卓から中国70年の変貌を探る
政治・経済・文化の交差点=「食」。計画経済下の配給制度から世界一の胃袋へ、変転極まりないマクロ。その一方で、家庭料理や行事食には伝統や人のつながりが残る。詳細な事例調査や個人史からたどる、庶民の日常と変化。ミクロな視点から社会史を描く、貴重な論考。
*********************************************
まえがき
食は私たちの日常に欠かせない営みでありながら、その背景には文化、歴史、経済、そして社会構造が深く刻まれている。特に、中国のように広大な国土と多様な民族を有する国では、食は単なる栄養摂取の手段を超え、時代ごとの価値観や社会の動向を映し出す鏡のような存在である。
本書は、中国北部の都市・天津市を事例とし、一九四九年の中華人民共和国成立から二〇一八年までの約七〇年間にわたる都市住民の食生活の変遷を描くものである。その歴史的背景と文化的意義を明らかにし、「食」という視点から現代中国の社会や文化を理解する一助となることを目指している。
なぜ「食」が現代中国を理解するうえで重要なのか。その理由の一つは、食が政治・経済・文化の交差点に位置しているからである。たとえば、計画経済下で実施された食物配給制度は、国家が個人の日常生活にどのように関与していたかを示している。一方、改革開放後の市場経済の導入は、食卓に多様性と豊かさをもたらしたが、新たな階層間格差や健康問題も生じさせた。近年では、デジタルメディアを通じた食情報の普及が、人々のライフスタイルや食材選択に大きな影響を与えている。このように、「食」という視点から、中国社会の変遷や人々の暮らしの変化を読み解くことができる。
日本における現代中国の食に関する研究は、一九七〇年代以降、活発に行われてきた。しかし、多くの研究は、地域性・民族性を中心とした料理文化や、グローバル化による外食産業の変容、文化遺産としての食文化の保護・継承などに焦点を当てている。一方、都市部の家庭における食事の変遷を詳細に記録した民族誌的研究はまだ少なく、とくに毛沢東時代(一九四九〜一九七六年)の都市部における家庭料理の実態については、十分な資料が存在しない。
こうした課題を克服するため、本書では現代中国の縮図ともいえる天津市を対象に、家庭の日常食と行事食を中心とした調査を行った。天津市は首都北京の喉元に位置し、交通の要衝として発展し、二〇世紀前半の中国北部における経済と政治の中心地となっていた。一九四九年以降は直轄市として中央政府の管轄を直接受け、新たな政策を施行する試験台ともなっていた。特に、食物配給制の実施と廃止に関して、天津市は最初に実施した四都市の一つであり、最後に廃止された都市でもある。
筆者は約一四ヵ月間にわたり現地調査を実施し、六二世帯計一五六人の食事構成に関する統計データ、二九世帯における参与観察の記録、五〇代以上の住民二〇人のライフヒストリー、食物配給に関わった関係者の証言、実際に使用されていた配給券・購入証・生活用品、地方誌や公文書など、多様なデータを収集した。これらをもとに、一九三〇年代以降の天津市民の家庭食事の持続と変化のメカニズムを探るとともに、毛沢東時代の都市部の食と日常生活の実態を明らかにする。また、社会主義体制下の一般市民が、限られた食料のなかでどのように工夫し、家庭の食生活を営んでいたのかも描き出す。
本書は、二〇二〇年に総合研究大学院大学文化科学研究科研究科長賞を受賞した博士論文を基に改稿されたものである。出版までの五年間にも、中国社会はかつてないほど急速な変化を遂げた。新型コロナウイルス感染症の世界的流行は、中国における食物供給システムや物流、外食産業に深刻な影響を及ぼした。ロックダウンや移動制限により、都市住民はオンラインショッピングや宅配サービスを活用するようになった。その一方で、配給制時代の食料確保の知恵を生かし、必需品の買いだめや隣人との物々交換、保存食の手作りなど、多様な対応を行った。これは、毛沢東時代の影響が現在の中国都市部にいまだ色濃く残っていることを示唆している。
そこで、本書を通じて、これまで日本ではほとんど知られてこなかった毛沢東時代の庶民の食事の実態を明らかにするとともに、当時培われた価値観や生活意識が、現在の都市住民の食行動にも受け継がれていることを伝えたい。特に、過去の食卓の記録をたどることで、パンデミックの影響や国家統制の再編が、今後の中国社会や人々の食生活にどのような変化をもたらすのかを考察する新たな視点を提供できればと考えている。
さらに、本書は中国食文化に関する研究にとどまらず、食を通じた社会主義国家の社会変遷の理解を広く読者に提供することを目的としている。近年、欧米圏や日本、中国の研究者は、旧ソ連や東欧諸国に加え、中国やベトナムなどのアジア諸国にも注目し、(ポスト)社会主義国の食と日常生活についての比較研究を進めている。本書がそうした研究動向の一助となれば幸いである。
*********************************************
著者紹介
劉征宇(りゅう せいう・LIU Zhengyu)
1985年、中国天津市生まれ。
2020年、総合研究大学院大学文化科学研究科博士後期課程修了。博士(文学)。
専攻は文化人類学、食文化研究、中国及び東アジア地域研究。
現在、国立民族学博物館外来研究員、龍谷大学非常勤講師、アジア食学学会(The Society of Asian Food Studies)副事務総長。
編著として、『社会主義制度下的中国飲食文化与日常生活』(国立民族学博物館、2018年、共編)、論文として、「食のドキュメンタリーから美食のショートビデオへ:中国における食文化発信の多元化」(『中国21』56号、2022年)、「現代中国の食を対象とする研究の動向」(『立命館食科学研究』4巻、2021年)、「Western Cuisine Culture in Contemporary China : A Case Study on Haute French Cuisine in High-class Hotels and Restaurants in Urban Tianjin」(The Spread of Food Cultures in Asia (Senri Ethnological Studies No. 100), edited by Kazunobu Ikeya, National Museum of Ethnology, 2019)など。