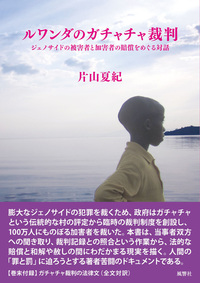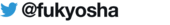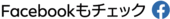目次
凡例/地図
序章
はじめに
一 ルワンダという国
二 ジェノサイド後の和解と協応行為
三 本書の構成
第一章 ルワンダのジェノサイド
一 ルワンダの「民族」問題
二 独立後の状況
三 ジェノサイド後の復興と続く暴力
《被害者と加害者の賠償の語り Ⅰ》
第二章 聞き取り調査と裁判記録の照合
一 聞き取り調査
二 追悼と想起
三 ガチャチャ裁判の裁判記録の閲覧
四 バナナと人の共生関係
小括
《被害者と加害者の賠償の語り Ⅱ》
第三章 伝統的なガチャチャからガチャチャ裁判へ
一 伝統的なガチャチャ
二 独立からジェノサイドまで
三 ジェノサイド終結後
小括
《被害者と加害者の賠償の語り Ⅲ》
第四章 ガチャチャ裁判の法律と賠償をめぐる対話
一 法律を論点にする賠償をめぐる対話
二 ガチャチャ裁判に関連する法律
三 ガチャチャ裁判の運営
四 賠償をめぐる対話がいかに行われているか
小括
《被害者と加害者の賠償の語り Ⅳ》
第五章 協応行為と境界線の考察
一 歴史のなかで引かれた境界線
二 賠償をめぐる対話の協応行為
小括
《加害者の賠償の語り Ⅴ》
終章
一 本書のまとめ
二 真の和解とは──修復的司法、そして人間の安全保障へ
《被害者と加害者の賠償の語り Ⅵ》
別章 これまで蓄積されてきた研究とこれからの研究
一 ジェノサイドとは
二 ジェノサイドの犯罪をどのように裁くのか
三 これから必要とされる研究
あとがき
参考文献
略語表/略年表
索引
●付録(巻末ヨコ組み)────
法律文の構成目次
掲載にあたって
ガチャチャ裁判の法律文
前文
第1部 本基本法が適用される犯罪(第1~2条)
第2部 ガチャチャ裁判の設立、組織、管轄及び他機関の関係(第3~50条)
第3部 犯罪の起訴と訴訟手続き(第51~96条)
第4部 雑則、経過規定、最終規定(第97~106条)
付 裁判のための文書フォーマット
1. ガチャチャ裁判の起訴状
2. ガチャチャ裁判の賠償の合意文書
3. ガチャチャ裁判の召喚状
内容説明
人間の「罪と罰」に迫るドキュメント
膨大なジェノサイドの犯罪を裁くため、政府はガチャチャという伝統的な村の評定から臨時の裁判制度を創設し、100万人にものぼる加害者を裁いた。本書は、当事者双方への聞き取り、裁判記録との照合という作業から、法的な賠償と和解や赦しの間にわだかまる現実を描く。人間の「罪と罰」に迫ろうとする著者苦闘のドキュメントである。【巻末付録】ガチャチャ裁判の法律文(全文対訳)
*********************************************
まえがき
数ある本の中から、「ガチャチャ裁判」という耳慣れないタイトルの本書を手に取って頂きありがとうございます。本編に入る前に、この本を書くことになったいきさつを少しお話します。
自身の話になりますが、幼いときから人と人が争っているのをみると悲しくなり泣き出す子どもでした。物心がつくころには「人と人はなぜ争うのか」という疑問をもつようになりました。
高校生のとき、母が切り抜いてくれた新聞記事にアフリカ諸国で紛争が多発していること、一九九四年にルワンダでジェノサイド(集団殺害)が起こったことが書かれていました。その記事は「アフリカの紛争がもしすべて解決すれば、世界はもっと平和になるだろう」と締めくくられていました。アフリカの紛争地で取材を続けている記者の祈りが込められたような一文が、私にアフリカへの関心を向けさせました。それとともに、この関心を学ぶことで「人と人はなぜ争うのか」という疑問に答えを出すことができるのではないかと思い、アフリカについて学べる大学へ進学しました。
大学でアフリカの紛争について学ぶなかで、あの新聞記事に書かれていたルワンダのジェノサイドに関する論文に出会いました。武内進一教授の論文「ルワンダにおける二つの紛争――ジェノサイドはいかに可能となったのか」[武内 二〇〇四]は、なぜジェノサイドが起こったのかという問いにダイレクトに答えを出していました。ルワンダ独立期の革命と一九九〇年代の紛争が比較され、国家の仕組みや国際情勢の変化がジェノサイドを引き起こしたことが分かりやすく書かれていました。「そうだったのか」と合点がいったことを今でもよく覚えています。この論文に出会い、興味関心のあることを追求していく研究職を志すようになりました。
関心を抱いたルワンダを見てみたい思いに駆られ単身で現地を訪れると、凄惨なジェノサイドが起こったとは信じられないほど平穏な風景が広がっていました。紛争後の社会がどのようにつくられてきたのかを知りたいという動機から、ジェノサイドを経験した人々に直接話を聞き取る調査を続けてきました。
被害者から苦しみや痛み、加害者から背負う罪の重さを聞くと、ジェノサイド後も同じ村で暮らしていくことがどれほど難しいことであるかを痛感させられました。「和解できる/できない」には到底おさまらないほど、被害者も加害者も厳しい現実を生きていることをひしひしと感じました。
そのような人々の語りや裁判記録の情報を集め続け、博士論文を書き上げたときには一〇年が経過していました。ルワンダのことを一般の人にも知ってもらうために博士論文のガチガチした文章と構成をできる限り書き直し、今回の出版に至りました。
本書のタイトルである「ガチャチャ裁判」は、ルワンダのジェノサイドに加担した民間人をローカルレベルで裁いた裁判です。判事を務めた者たちは、検事や裁判官や弁護士といった法律資格をもたない「普通の人々」でした。さらに一八歳以上の住民全員がガチャチャ裁判のためにジェノサイドの被害を事細かく調べることを義務付けられました。通常の裁判では一〇〇年かかると言われたところを、ガチャチャ裁判はわずか一〇年で一〇〇万人を裁いたのです。同じ村で暮らしてきた者を容疑者として裁くことは想像を絶するほどに過酷な取り組みですが、住民はその試練に耐えました。ガチャチャ裁判の制度については研究者が問題を指摘していますが、本研究はガチャチャ裁判を運営した住民の知られざる奮闘に着目しています。
このような住民の奮闘を知ったのは、住民が作成したガチャチャ裁判の裁判記録を読み込んだからです。裁判記録は非公開ですが、ルワンダ政府から許可証を得て閲覧しました。その裁判記録には、ジェノサイドの加害者がどのような武器を使いどのように殺害したのか、どこに遺体を遺棄したのか、どのように財産を略奪し破壊したのか、一つ一つの事件を調べ尽くした情報が手書きされていました。
一言で「裁判記録」といっても十数種類の文書から成ります。特に起訴状は何度もアップデートされ、法律資格を持たない「普通の人々」でも迅速に裁くことができるようなフォーマットになっていました。ルワンダ政府の許可を得て、裁判のための文書フォーマットを本書の巻末に公開しています。さらに、ガチャチャ裁判独自の法律文を日本語訳したものを巻末に掲載しています。文書フォーマットも法律文の日本語訳も他の本には掲載されておらず、私の知る限りでは本書が初公開となります。
*********************************************
著者紹介
片山 夏紀(かたやま なつき)
ルワンダでもらった名前はカイテシ(Kayitesi、世話の焼ける小さい人という意味)。
長崎県生まれ、大阪府育ち。
東京大学大学院総合文化研究科国際社会科学専攻「人間の安全保障」プログラム博士課程修了。2023年博士号取得(国際貢献)。博士論文は一高記念賞受賞。2024年度 第5回而立賞(東京大学学術成果刊行助成)を受賞し本書の出版に至る。
都留文科大学教養学部比較文化学科専任講師(4月~)。
著書に、『ルワンダの今:ジェノサイドを語る被害者と加害者』(風響社、2020年)。論文に、「ガチャチャ裁判が命じた賠償をめぐる当事者の交渉:ルワンダ・ジェノサイドに関連する罪の赦しと和解」(『アフリカレポート』2019年、第57巻、22-33頁)、「『ジャガイモをおいしくするもの』:笑いを誘うルワンダ詩」(『スワヒリ&アフリカ研究』2020年、第31号、1-16頁)、「スワヒリ語を話すルワンダ人」(『スワヒリ&アフリカ研究』2023年、第34号、70-87頁)など。