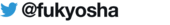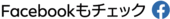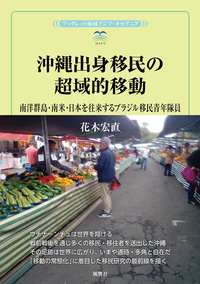
「移動の常態化」に着目した移民研究の最前線を、戦前戦後を通じ多くの移民・移住者を送出した沖縄にフォーカスして描く(近刊)
| 著者 | 花木宏直 著 |
|---|---|
| ジャンル | 人類学 |
| シリーズ | 風響社ブックレット 風響社ブックレット > ブックレット海域アジア・オセアニア |
| 出版年月日 | 2025/03/25 |
| ISBN | 9784894893672 |
| 判型・ページ数 | A5・84ページ |
| 定価 | 本体900円+税 |
| 在庫 | 未刊・予約受付中 |
| ネット書店を選択 |
|---|
目次
一 ブラジル移民青年隊の調査経緯
1 沖縄の自治体史移民編
2 沖縄移民研究センター
二 沖縄からの出移民史
1 移民から引揚げへ
2 戦後移民の送出
三 ブラジル移民青年隊の展開
1 事業概要
2 移住過程
四 八重瀬町出身青年隊員の動向
1 入隊から移民へ
2 居住地移動と職業変化
五 デカセギの展開
1 移民からデカセギへ
2 鶴見の地理的特徴
おわりに
注・参考文献
内容説明
ウチナーンチュは世界を翔ける
戦前戦後を通じ多くの移民・移住者を送出した沖縄。その足跡は世界に広がり、いまや通時・多角と自在だ。「移動の常態化」に着目した移民研究の最前線を描く、注目の論考。
*********************************************
はじめに より
一方、沖縄では第二次世界大戦後、南洋群島やフィリピンをはじめ各地からの引揚げに伴い人口が急増した。そして、一九四八年よりアルゼンチンへの呼寄移民の再開を契機としてしだいに出移民数が増加し、一九五〇年代以降はとくにブラジルへの移民が多数みられた。一九五四年にはボリビア計画移民が送出されるなど、琉球政府や海外協会による独自の移民事業が行われた。主な移住先は南米と、八重山諸島への開拓移住、日本本土への出稼ぎや集団就職などであった[石川 二〇一〇]。
このように、沖縄では歴史的背景や地理的条件の相違のため、日本本土とは異なる移民送出のあり方がみられた。そして、第二次世界大戦前から戦後を通じて多数の移民を送出し、ハワイや南米などの海外だけでなく南洋群島などの外地、日本本土をはじめ各地へ移住していた。沖縄からの出移民研究を進める上で、第二次世界大戦前と前後、海外と外地、日本本土への移民・出稼ぎの相互関係に注目することが重要である。
なお、日本からの出移民に関する近年の研究では、戦後移民に関する研究の進展がみられる。これらの成果に注目すると、移民は主に行政が主体となり募集を行う公募移住として送出され、農林省が中心的役割を果たしたことや、農家の二三男問題への対応、すなわち農家の非後継者の就業先の確保が送出の目的であったこと、これらの事業は満洲開拓移民との連続性がみられること、そして引揚者が移民の募集対象となったが彼らは再移住に抵抗感をもっていたことなどが指摘される[伊藤 二〇一三:二三一─二三五、安岡 二〇一四:一八二─一九〇]。また、第二次世界大戦前から戦後を通じて、部落差別や労働運動の当事者、炭鉱閉山に伴う失業者など社会問題の解決手段として移民送出が行われてきたという側面もみられた[遠藤 二〇一六]。
これらの研究を通じて、戦後移民の特徴の一つである公募移住をめぐる、第二次世界大戦前からの政治的背景の連続性や制度的課題が検討されてきた。しかし、それに応じた移民自身の動向にも注目し、検討を深める必要がある。なお、近年は南洋群島から引揚後に戦後開拓に従事した者や戦後移民となった者のルポルタージュが刊行されるなど、戦前から戦後を通じた日本人の超域的移動への関心が高まっている(たとえば、寺尾[二〇二三]など)。その一例として、本書では沖縄出身移民の超域的移動に注目したい。
本書の研究対象としてブラジル移民青年隊(以下、適宜「青年隊」と略して記す)を取り上げる。青年隊は第二次世界大戦後の沖縄で行われた公募移住による農業開拓を目的とした移民事業の一つであり、一九五〇年代半ばから一九六〇年代半ばにかけて三〇〇人を送出した。戦後沖縄の公募移住による移民事業では、ボリビア計画移民が三二二一人を送出しており最大規模である。一方、青年隊は国・地域別で最多の出移民数となったブラジルへの公募移住による移民事業であり、戦後沖縄を象徴する移民事業と位置づけられる。
写真1には『移民青年隊着伯二十五周年記念誌』に収録された一九六七年頃の青年隊員の様子を示した[在伯沖縄青年協会編 一九八四:九五]。金武村(現・金武町)出身者がサンパウロ市近郊でシャーカラと呼ばれる近郊農業を経営しており、農園ではトマトを栽培し、現地人の雇用がみられる。一方、どのような属性をもつ者が、どのような経緯で青年隊員となり移住したのであろうか。また、移住後はどこに居住し、どのような職業に従事したであろうか。移住前後を含む青年隊員自身の動向に注目する必要がある。
以上を踏まえ、本書はブラジル移民青年隊を通じて沖縄出身移民の特性を検討することを目的とする。その際、南洋群島引揚者との関わりを意識して検討を進める。本書を通じて、第二次世界大戦前から戦後にかけての、沖縄とオセアニア、南米などの超域的な地域間関係の一端を捉えるための話題提供になれば幸いである。
ここで、本書における「移民」の定義を述べたい。本書には、沖縄から海外だけでなく、南洋群島や満洲などの外地、日本本土という、さまざまな地域への移動が登場する。また、移動の目的も、出稼ぎや、出稼ぎを目的としながら永住した場合、当初から永住、永住を目的としながら帰郷することになり一時的滞在にとどまるなどさまざまである。そのため、移住先や移動の目的の違いに応じて「移民」や「移住」、「出稼ぎ」の語彙を使いわけることが難しい。そこで、本書では基本的に、海外移民のほかに、南洋群島や満洲など外地への移住、日本本土への出稼ぎも含めて「移民」と記す。ただし、文脈により、海外移民だけを指す場合と、外地への移住や日本本土への出稼ぎを含む場合がある。関連して、「移民」という概念の下に移住や出稼ぎの意味を含めているため、必要に応じて「移住」や「出稼ぎ」という表記を用いる場合がある。本書には移民に関するさまざまな類義語が登場し、読みにくさがあるかもしれないが、ご了承願いたい。
*********************************************
著者紹介
花木宏直(はなき ひろなお)
1985年、愛知県生まれ。
2013年、筑波大学一貫制博士課程人文社会科学研究科歴史・人類学専攻単位取得満期退学。
現在、関西学院大学文学部・准教授。博士(文学)。
主な業績:『離島研究Ⅴ』(海青社、2015年、分担執筆)、『生活文化の地理学』(古今書院、2019年、分担執筆)、『Insularity and Geographic Diversity of the Peripheral Japanese Islands』(Springer、2022年、分担執筆)、『離島研究Ⅶ』(海青社、2024年、分担執筆)など。
*********************************************
*********************************************
*********************************************
ブックレット海域アジア・オセアニア 「刊行の辞」
本ブックレットシリーズは、海域アジアとオセアニアを対象地域としている。ここでいう海域アジアとは、日本・琉球列島や台湾、東南アジア島嶼部といった海と島からなる海域世界、ならびにアジア大陸部の沿海部を指している。また、オセアニアは、南太平洋に浮かぶ島嶼群やオーストラリア大陸からなる一大海域世界でもある。本シリーズは、その両者を分けることなく、海を媒介としてつながる海域世界として捉え直している点に特徴がある。
海域アジア・オセアニアは、しばしば近代の陸地中心的な国家・地域観に基づき、中国、台湾、東南アジア、オセアニアなど、個別の研究対象地域に分けられてきた。だが、海域アジアとオセアニアは、古来より人類の移住、モノ、文化、宗教の移動を通してつながってきたエリアである。近年、両地域間のヒト、モノ、文化、情報の越境的な動きは、ますます加速している。本シリーズは、海域中心的な視点に立脚しながら、海域アジアとオセアニアの歴史的・現代的なつながりを描き出そうとするものである。
二一世紀は「太平洋の世紀」ともいわれるように、海域アジアとオセアニアは地政学的に極めて重要な位置を占めつつある。本シリーズでは、その各地域における開発や生態、食生活、災害といった人々と環境の相互的関係性、あるいは人々の移動に伴う越境の動態など、さまざまなトピックを扱う。そして、シリーズ全体として海域アジアとオセアニアの間の連環世界を捉えていくことで、従来の地域概念や蛸壺化しつつある地域研究の枠組みを超えた、新たな地域研究の在り方とその方法を模索していきたい。
海域アジア・オセアニアは「境界をもたない」地域概念でもある。したがって、本シリーズが想定する海域アジアやオセアニアの範疇を超えて拡がる世界も、視野に含まれる。本シリーズは、個々の研究者の最新の研究を通して、新たな地域研究の枠組みを模索することを目標の一つとしている。その一方で、その最新の研究成果をわかりやすく伝えることで、広く社会に向けて海域アジア・オセアニアの諸相を知っていただきたいと願っている。本シリーズが、アジアとオセアニアをつなぐ海域世界への理解に、少しでも役立てられることがあれば幸いである。
二〇二四年三月
「海域アジア・オセアニア・ブックレット」ジェネラル・エディター
小野林太郎・河合洋尚・長津一史・古澤拓郎
*本ブックレットシリーズは、大学共同利用機関法人・人間文化研究機構で推進されている機関プロジェクトの1つ「海域アジア・オセアニア研究プロジェクト」(拠点機関:国立民族学博物館・東洋大学・京都大学・東京都立大学)が、企画編集しているものである。