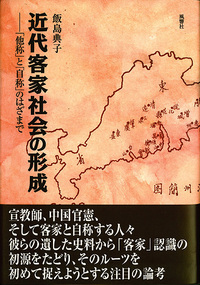目次
序論
一 客家の名称を巡って
二 客家研究の濫觴
三 先行研究に見る多角的な研究視点と論題の多様化
四 客家研究における定義の問題点
五 問題提起と研究方法
第一章 宣教師文書に見る客家
一 宣教師と客家の接触にあった背景
二 ギュツラフと「客」の邂逅
三 アメリカン・ボード(美国公理会)の初期客家認識
四 Hakkaという名称の登場
小結
第二章 西江デルタの叛乱と動乱にみる客家
一 西江に於ける土客の相克──その発端
二 咸豊以降の土客衝突激化
三 天地会と広東客家
四 西江北岸の客土緩衝地帯
五 赤渓庁史再考
六 アメリカン・ボード宣教師の見た広州客家
小結
第三章 広東東北部の客家語圏──その社会・経済
一 はじめに
二 東北部の概略と先行研究
三 東北部の経済と社会
四 清代の銀流通と広東
五 東北部の「鉱賊」
六 嘉応州の石炭採掘業
小結
第四章 「客人」の自己像とその歴史
一 「客」意識の濫觴
二 自発的な組織設立の動きとその背景──嘉属会館と崇正総会
三 崇正総会の発展と大埔人の位置づけ
四 梅県の教科書にみる自己像
五 葉亜来再考
六 ペラとペナンの「嘉応州人」と嘉応州会館
小結
結論
後書き
参考文献
付録
索引
内容説明
宣教師、中国官憲、そして自らを客家と称する人々が遺した史料を元に、それぞれがいつ、どのように「客家」という存在を認識したかについて詳細に検討。社会・経済の視点から、客家集団を客観的な存在として初めて捉え得た注目の論考。
*********************************************
はじめに
中国南部(華南)社会や華僑に多少でも興味を持つとどこかで「客家(ハッカ)」という名称にぶつかるであろう。或いは東南アジアの華僑分類としてもこの言葉を目にするかもしれない。華僑分類も幾つかの方法があるが、広東・福建など他の分類項目が地名を冠しているのに対し、客家だけがこの法則に当てはまらない。この例外的な名称が様々な憶測を呼んだのか、客家は近代以降、漢民族の謎めいた集団として屡々日本でも紹介されてきた。そうした中、一般の啓蒙書も含めまた客家(と自称する人々)が共通して指摘しているのは客家が他の漢民族から差別されてきたため、人一倍勤勉に働く事によって偏見と闘わねばならなかったという言説が絶えず喧伝されている。
客家に限らず、「少数派」は概して激しく、時に矛盾するような毀誉褒貶がつきまとう。客家と同様、地域名や国名を冠しないユダヤ人にまつわる言説が多種多様にわたることはここで敢えて詳述しないが、いずれにせよこうした言説ではユダヤ人の連帯感や均一性が事実以上に強調されている感がある。かくしてユダヤ人の多様性には目が向けられないまま、彼らに関する偏見や幻想は増幅されがちなのであるが、こうした傾向は客家評に一脈共通する所があり、客家自身も自らを「東洋のユダヤ人」に擬する向きがあるのも故無き事でないかもしれない。
客家についての紹介は如何に彼らが差別を克服して今日の成功を収めたかという賛美が幾度と無く強調されてきたが、「勤勉」や「団結心」は何も客家の専売特許有ではない。とは言え華南社会の中、ひいては中国全土の中の少数派でありながらもこれだけ中国内外で彼らが注目を集めてきたのはそれなりの理由があるのだろうし、事実日本の外務省も一九三〇年代には客家に関しての調査をまとめており、その注目度の高さ自体ある種の社会的な成功を意味している。
それでは彼らが注目を集めるに至った経緯を「史実」から冷静に見つめて出来る限り客観的に客家の姿を明らかに出来ないものだろうか、と考えたのが本書の出発点であった。
勿論客家に関しては既に言語学、文化人類学の分野では幾つかの優れた先行研究が発表されているが、歴史学の方面から客家を対象とした研究はこの上記二分野のそれより更に少数である。
本論でも詳しく触れるが、そもそも客家という言葉が中国官憲の文書に登場するようになるのはさして昔の事ではなく、管見の限り一九世紀以降である。それまで客家語を話していても、何故自称客家と公に名乗る人々が殆どいなかったのか、何か別の自称を使って自分たちを表現していたのか、など明らかになっていない点も多かった事に加えて、そもそも客家を扱うのに関して「誰(どのような集団)を客家と呼ぶのか」についてどのように定義すべきかの疑問が投げかけられていなかったのである。従来、中国本土では主な客家語圏としては広東東部、福建西部が挙げられていたが、近年、江西も客家のルーツの一地域として名乗りを挙げ、二〇〇四年には同地で世界的な客家の親睦会が開かれるなど、客家を標榜する人々やその団体が雨後の筍の如く増えている。こうして従来客家を標榜しなかった地域が新たに名乗りを挙げるのは今まで──彼らが知る限り──「客家」を名乗ることに躊躇いがあったのか、自分が客家だと考えた事がなかったのか、という疑問も前の二つの問題点を更に深く追求したいと考える動機となっている。
こうした疑問を解決するため、本論では対象とする一九世紀初頭から二〇世紀初頭までの華南事情を出来る限り幅広く網羅し、とくに客家という表現が使われていなくても、先行研究で明らかに客家語圏とされる地域を対象とした記述から、その土地の住民の動向を見いだして抽出するという方法をとった。客家を名乗る人々が自ら書き表した史料は二〇世紀になるまで極めて少数であり、本書で使用した文献の大半は西洋人宣教師や官憲側の文書で、いずれもあくまで客家を「他者」として見つめたものである。西洋人宣教師の文書は殆どが本国への活動報告ないし彼らの見聞を踏まえての中国事情紹介である。宣教師の視点は中国の外来者として彼らが見た事実のありのままを伝え、どのように彼らが「客家」を知ったのか、どのような点を彼らの特徴として見いだしているか、を知る上で大変貴重な史料である。
一方、中国官憲の記録は華南の様々な社会集団──広東語話者、畭族等──の中での客家を描いており、彼らが華南社会の中でどのような軋轢を生じていたのかをここから知る事が出来る。勿論、宣教師・中国官憲双方の見解とて全く客観的とは言えないであろうし、多少の先入観や誤解は免れないであろうが、客家を標榜する人々が漸次記録を残すようになる民国期以前としては両者とも貴重な手がかりとなる文献である。また民国期以降になると客家自身が徐々に社会に向かって自分たちが何者であるかという主張を発信してゆくので、彼らが自分達の過去をどのように振り返って記すかを見ることが出来、考察する側の視点を更に複眼的にしてくれている。
本書は以上の三種の資料をもとに、清代中期から民国期にかけての華南事情を扱った先行研究を援用した上で、客家と呼ばれるようになった人々の社会がどのように形成されたかを論じ、主観的な毀誉褒貶を脱して彼らの実像の一端を明らかにしようとした試みである。
周知のように冷戦終結後は世界のあちこちで民族紛争が起こり、少数集団(民族)に対する報道は増えつつある。少数集団は何ゆえに注目されてきたのか、少数集団側はどのように彼らを社会に認めさせる事が出来るのか、といった様々な問題がマスコミの報道を通して浮き彫りになってきた訳であるが、少数集団がいつ頃、どのようなきっかけで自分たちのアイデンティティを強く社会に向けて主張するようになったのか、「自称」と「他称(屡々差別の語感を伴う)」のどちらを(或いは両方を)自分を表す名称として受け入れたのかを考察する事は歴史の一側面を知る切り口ともなるのではないか。客家はその一つの例に過ぎないが、本書の試みが世界の少数集団を見つめ直す上で何らかのヒントになれば望外の喜びである。
*********************************************
著者紹介
飯島典子(いいじま のりこ)
1965年生まれ
2004年、一橋大学大学院社会学研究科博士課程修了(社会学博士)
主要論文に「清代台湾開拓社会における客家人」『アジア文化研究』(国際アジア文化学会、1996年6月第3号)、「19世紀宣教師文書から見た客家」『一橋論叢』(2003年8月号、第130巻第2号)、「中国及び海外における客家語話者の親睦団体成立過程に関する一考察:祖籍や出身地を超えた「客」の概念」『華僑華人研究』(第1号、2004年8月)等。